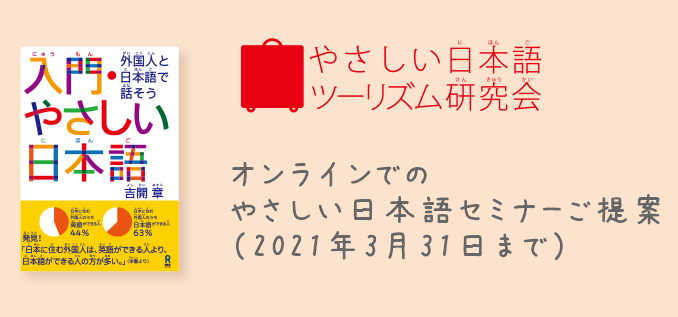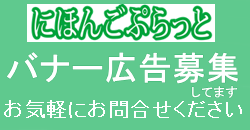日振協の新理事長に選ばれた加藤早苗氏に聞く 「日本語学校は多文化共生社会のハブになるべき」

日振協の新理事長に選ばれた加藤早苗氏に聞く 「日本語学校は多文化共生社会のハブになるべき」
日本語教育振興協会(日振協)の新しい理事長にインターカルト日本語学校校長の加藤早苗氏が選ばれた。約30年にわたり理事長を務めた佐藤次郎氏からのバトンタッチである。日本語学校が国の認定校になるなど、日本語教育の在り方が大きく変化する中、日振協のトップとしてどのようなリーダーシップを発揮するのか。加藤氏に考えを聞いた。
(聞き手は、にほんごぷらっと編集長・石原進)
——日本語教師、日本語学校の校長、加えて日振協の理事長という重責を背負うことになりました。理事長就任から半年余りがたちます。新理事長として、いまどんなことに取り組んでいますか。
加藤氏 日本語教育機関認定法ができ、日本語学校が認定教育機関として再出発しなければなりません。政府の認定を受けるためには手続きが必要ですが、認定率はまだ低いのが現状です。このため日本語学校の申請手続きを促すためのセミナーを全国で展開しています。そして、これからの日振協は「研修」と「評価」を中心事業にしていきます。研修事業は系統的・段階的に人材育成をするのを目的とし、評価事業は認定日本語教育機関の質の維持・向上が目的です。この2つを日振協の大きな柱としました。
――認定日本語教育機関への認定申請の期間は5年です。すでに2年が経過しました。認定状況はいかがですか。
加藤氏 文部科学省によると、今年10月現在で認定申請した日本語教育機関は73機関で、留学で認定を受けたのは19機関です。まだ様子見しているケースが多いのが現状でしょうが、申請の仕方がよくわからずに躊躇している教育機関も少なくないようです。
——全国で展開しているセミナーでは、具体的にどんなことを行っているのでしょうか。
加藤氏 全国各地での情報交換会を兼ねた認定日本語教育機関の申請対策セミナーです。9月から10月にかけて近畿、九州・沖縄、中国・四国、東京・関東・甲信越の地区別でセミナーを開きました。11月には東海・北陸、北海道・東北でも開催します。セミナーでは、実際の申請プロセスで起こりがちな課題を具体的にお伝えするほか、参加校同士の情報交換・交流の時間も設けています。参加は、総計260機関、約450人になる予定です。
——認定日本語教育機関になると、日本語学校の在り方も変わってくると考えていますか。
加藤氏 国から認定された教育機関になるわけですからステータスが上がることになるのでしょうが、同時に責任も重くなります。日本語教育の質をより高めなければなりません。また、認定日本語教育機関になるということは、その時点で一旦すべての日本語学校が同じスタート地点に立つということです。そうすると、従来の学校法人と株式会社といった設置形態による「制度上の区別」などをどう考えるのか。業界として検討すべき課題も生まれてくるように思います。
——認定日本語教育機関の認定をめぐる現状について、感じることがありますか。
加藤氏 告示校としてやってきた日本語学校より、新規校の方が、認定率が高いことには違和感を覚えています。告示校にはまだ申請していない学校が少なくないようですが、それぞれの学校に、今まで築いてきた教育の考え方、そこでの実績があるわけですが、それが認定のための審査要件と必ずしも合っていなくて苦労しているという声があります。一方、新規校には「過去の実績」がありません。ある意味で「足かせ」になるものがありません。これまで頑張ってきた日本語学校にすれば、複雑な思いを抱かざるを得ないわけです。
——日本語学校は業界団体が6つあり、ゆるやかなまとまりとして日本語教育機関団体連絡協議会が発足しました。この連絡協議会を法人化して業界団体を一本化しようという動きがあると聞きましたが。
加藤氏 私自身はまず、それぞれの業界団体の上に一つのまとまった組織を置く必要があると考えています。日本語学校も認定日本語教育機関として再出発した場合、留学生の日本語教育だけでなく、働く外国人や生活者の日本語教育などもミッションとなる可能性があります。多文化共生の社会づくりの基盤を支える取り組みを日本語学校が担っていくことになるわけです。
その時、行政や企業などに日本語学校としての要望を伝えるとしても、業界団体としてまとまって対応しなければ話が進展しません。社会的な責任を果たすためにも業界団体としての一つのまとまった組織は必要です。
新年度までに新たな法人組織を立ち上げられたらと考えています。6団体でつくる現在の連絡協議会がそっくり法人化できるかどうかはわかりません。6つの団体にはそれぞれ組織としての考え方がありますから。しかし、まとまれるところで、できるだけ早くまとまる方がいいでしょう。
——政府は多文化共生社会をつくるための一丁目一番地が日本語教育だと言っています。日本語学校はこれからさらに重要な役割を担うことになります。日本語教育はどうあるべきか。お考えがあればお聞かせください。
加藤氏 これから日本人だけの日本社会ではなくなる中で、日本語教育機関の卒業生は、しっかりと日本語を学び、日本文化を理解し日本社会の慣習に馴染んでいるということで、社会を支える構成員としてより担保されたものがあるわけです。彼らはそういう存在であるということを、私たちは言っていくべきですし、もっと認められていくべきだと思います。
そうした意味で、一つ一つの学校も、日振協も、一つにまとまるであろう組織も、日本語教育を下支えする立場として、もっと企業や社会、一般の日本人に向けて、多文化共生社会のあり方を伝える機会を作っていく必要があります。日本語教育は、重要な社会インフラです。そして日本語学校は、多文化共生のハブになるということだと思います。
【一般財団法人・日本語教育振興協会(日振協)】中曽根政権が1983年に「留学生10万人計画」を策定したのを受けて日本語学校(日本語教育機関)が急増。制度が整備されていなかった時期で、就労目的の留学生が多数来日した。このため法務省入管局が留学生の受け入れを差し止めた。この結果、授業料や渡航費を業者に支払ったのに留学ビザが出ないケースが多発するなど混乱。1988年には中国の上海では日本の総領事館を抗議デモが取り囲むなどして日中間の政治問題になった。この騒動は上海事件と呼ばれる。
こうした中で1989年に日振協が発足。その後、法務省の業務を補完する形で留学生の審査・認定事業を請け負った。ところが、民主党政権時代の「事業仕分け」によって、日振協が行っていた審査・認定業務が打ち切りとなり、日振協から日本語学校の脱会も相次ぎ、新たな業界団体が設立された。現在、日振協を含め6つの団体が存在。6団体がゆるやかな連絡組織として日本語教育機関団体連絡協議会を設立し、コロナ禍で中断していた留学生受け入れの再開などを政府に働きかけた。日振協は最も歴史と伝統がある中核組織。文部科学省の幹部だった佐藤次郎氏が1996年に理事長に就任。2025年に退任するまで、リーダーシップをとってきた。