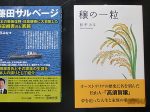日本語議連や政府、官庁、自治体、業界団体、学会、研究会、学校、出版社、観光協会、商工会、NPO団体、企業、その他公益法人などが主催する、教師向けイベント、留学生向けイベント、一般向けのお祭り、観光地イベントなど、日本語教育や、異なる文化を楽しむイベントを掲載いたします。
|掲載申込はこちら|
7月
20
日
【!!追加募集!!】NPO法人日本語教育研究所 主催文部科学省委託 令和7年度現職日本語教師研修プログラム普及事業 就労者に対する日本語教師【初任】研修 就労者に対する日本語教師養成 –日本語教育研究所の多様な研修実績及び人材を活かしたビジネス日本語教育/指導- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ この研修は、これから新たに就労者に日本語を教えたいと考えている方を主な対象としています。スキルアップにぜひお役立てください。 再受講をご検討の方へ 本研修はこれまでに弊所の研修をご受講された方も、再度ご参加いただけます。 実際に現場に出て、もう一度確認したいことなども出てきているのではないでしょうか。 さらに実践的な指導力を高める良い機会となりますので、ぜひご検討ください。 ─────────────────── ■期間 2025年7月20日(日) ~ 2026年2月8日(日) *日程等の詳細は、募集要項のリンク先からご覧ください。 ■対象 日本語教育機関認定法に基づく「登録日本語教員」を対象としますが、本法の経過措置期間内(令和10年度まで)は、令和6年度までに下記を修了した方も対象とします。 1)日本語教師として下記のいずれかの要件を満たす方 ①大学/大学院で日本語教育に関する教育課程を修了し、大学/大学院を卒業/修了した方 ②大学/大学院で日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、大学/大学院を卒業/修了した方 ③公益財団法人日本国際教育支援協会「日本語教育能力検定試験」に合格した方 ④学士の学位を有し、日本語教師養成講座 420 単位時間以上を修了した方 2)原則として、就労者への日本語教育歴が0~3年未満の方 ■定員 100名 ■受講料 20,000円(税込) ※教材費込み ■申込方法 以下のリンクからお申し込みください。 https://forms.gle/JWtnJ6WzzCNQvQx88 ■申込締切 2025年6月30日(月)【募集期間延長しました!!】 ■募集要項 https://docs.google.com/document/d/1uHn1k6zdRIgcQ2-lK5Uyr1Qa5vlwzXCFvKEUw3UjJVU/edit?usp=sharing ■お問い合わせ NPO法人 日本語教育研究所(研修事務局) nikken.kenshu@gmail.com
8月
7
木
日本語学校教育研究大会では、各日本語教育機関における実践・事例の報告の機会として、発表の場を設けています。 意見・アイディア交換の場としてぜひご活用ください。 皆様からのご応募お待ちしております。
 ︎「
︎「 ︎ 現場の“今”を意識した研修プログラムにより、
︎ 現場の“今”を意識した研修プログラムにより、 ︎ グループワークでは経験別や所属学校の属性別のグループを構成す
︎ グループワークでは経験別や所属学校の属性別のグループを構成す