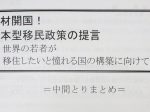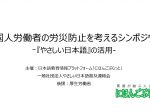ベトナム人技能実習生制度のゆがんだ実態
- 2017/11/24
- 時代のことば
- 外国人技能実習機構, 外国人技能実習生制度, 技能実習生
- 1,960 comments

【寄稿者:実習生送り出し機関日本語教師】

外国人技能実習生制度について(外部リンク)公益財団法人国際研修協力機構
ベトナム人技能実習生の数が中国人技能実習生の数を抜いた
1993年からの研修生時代(在留資格「研修」創設)も含め、実習制度が始まって25年が経ち、本年11月1日から外国人技能実習機構の下、新制度に移行することとなりました。「介護」をはじめ、「ビルメンテナンス」や「自動車整備」など、新たな職種も続々と追加され、今後も増加していく流れになると思われます。
平成28年末時点で、228,589人の技能実習生が日本に在留しています。また国別では、これまで長きに渡り圧倒的多数だった中国をベトナムが抜きました。(ベトナム : 38.6%、中国 : 35.4% 法務省より)
今後、数年はベトナム人技能実習生の増加が継続すると見ていますが、日越が抱える問題は決して少なくありません。筆者は、渡越後約4年、現職も含め3社の送り出し機関に勤めてきました。実際に見聞きし、筆者が感じる技能実習生制度が抱える特に大きい問題は以下の3点です。
- 入国前の教育の質
- 実習生が抱える法外な借金
- 悪質な送り出し機関、監理団体、受け入れ企業
入国前の日本語教育の質に課題
まず、1について、ベトナム全土には、ベトナム政府認定送り出し機関が239社存在します。(外国人技能実習機構HPより)
しかし、ベトナム全土には350人程度の日本人教師(国際交流基金の2016年報告による。有資格か否かは不明)しかおらず、大学などの高等教育機関、留学生派遣企業などを除くと、送り出し機関239社に最低一人の日本人教師すら足りなくなります。
*年間派遣人数が1,000人を超えるマンモス校は、一社で、10人を超える日本人教師を雇っていることもあります。
また、ベトナムの企業へのインターン者やベトナムの大学への留学生、セカンドライフをベトナムで過ごす早期退職者など、お手軽バイト気分で、教師としてのバックボーンがない日本人が送り出し機関の教壇に立っていることもあります。内容は日本語教育とは程遠いただの「おしゃべり」に過ぎない場合もあります。
ベトナム人教師についても、教授法を学んだわけでもなく、元実習生や元留学生など「日本語ができるから」「求人が多いから」という理由で、日本語教師をやっているベトナム人が多いように感じます。
*ベトナムでは、ベトナム人向けの日本語教授法を学べるのは1つ大学の専攻だけであり、内容も初級レベルであり、日本のように民間企業による養成講座はありません。
また、送り出し機関の教師の入れ替わり率の高さは異常です。前職の場合、1年勤めた期間で、6名が辞め、7名の新しい教師が入り、現職の2年間でも、11名が辞め、9名が新しく入っています。離職率、入れ替わり率の高さは「給料の問題」が大きく、愛社精神も日本ほど高くなく、さらに向上心が日本より旺盛なため、自分の能力に見合った仕事・待遇ではないと感じると早々に転職していきます。これまでの最速記録は1週間です。
また、教師自身の日本語にしても、送り出し機関のベトナム人教師自身も、以前は、元実習生のベトナム教師に習っているわけですから、誤った知識のまま、進んでしまうこともあります。カリキュラムにしても、半年で、N4を修了させることもできないペースです。
介護を除く、現行職種には入国時の日本語要件が設定されておらず、極論、挨拶程度しかできずとも入国できてしまいます。送り出し機関は「修了証」を発行しますが、あくまで、「○○時間勉強した」という内容であり、日本語能力についてのものではありません。
実習生が抱える法外な借金問題
2の法外な借金について、最近、様々なメディアで、報じられていることもあり、徐々に明るみに出てきている印象がありますが、その内訳や内容についてはあまり触れらていません。まず、実習生の負担する費用の中で一番大きいものが、ベトナム法で3,600USDと規定されている俗に言う「手数料」です。法定は3,600USD(DOLAB 海外労働管理局より)ですが、現在の相場は5,000~6,000USDです。
これまで、働いた3社及び、他社経由で日本へ入国した実習生から実際に聞いた話などを鑑みた結果、100%法定手数料を守っている送り出し機関は存在しませんでした。
*「100%ではない」というのは、職種・監理団体・受け入れ企業によって、手数料の金額が個別に設定されているためです。そのため、一部法定の3,600USD設定となっていることもあります。
また、日本へ行きたいベトナム人を送り出し機関に紹介するベトナム人ブローカーがおり、受け入れ企業による採用面接に合格した時点で、実習生は500USD~2,000USDをそのブローカーに支払います。またこのブローカーが一人ではない場合もあり、実習生はそれぞれに払わなければならないこともあります。
日本人ブローカーは、監理団体や受け入れ企業を送り出し機関に紹介し、実習生が採用され、入国した際に一人当たり500USD~2,000USDという報酬を送り出し機関から受け取ります。送り出し機関は利鞘を減らしたくないため、ブローカーに支払う報酬をそのまま実習生が支払う手数料に上乗せする場合があります。最悪の状況を考えれば、100万円は簡単に超えていきます。月収が2万~3万円が当たり前のベトナムにあって、尋常ではない金額です。
送り出し機関はこうしたベトナム人ブローカーを把握しきれず、また罰則もないため、野放し状態であり、日本の大半の監理団体もこうした現状を知っていながら、我関せずと具体的な手を打つということをしていません。
悪質な「送り出し機関」「監理団体」「受け入れ企業」
3の悪質な送り出し機関とは、法外な手数料を設定し、教育をおざなりにし、手数料を手に入れることしか考えず、客を選別せず、とにかく数ばかり追う送り出し機関をさします。
次に悪質な監理団体とは、実習生を採用して「あげる」から、キックバックを要求したり、法に定められた費用の値下げや支払いの拒否、過度な接待の強要などが挙げられます。キックバックは一人採用当たり500USD~1,000USDです。筆者の務める送り出し機関も、岡山県にある縫製業専門の監理団体からキックバックの要求をされたことが実際にあります。法に定められた費用とは、管理費(3年間毎月発生)、講習委託費(入国前の学費)、実習生入帰国時の航空券などです。実習生事業は監理団体からの実習生採用のオーダーがなければ、始まらず、また 送り出し機関が乱立し、安売り合戦をしているため、本来は対等であるはずの関係が、監理団体に力が傾いています。実際に、監理団体から言われた内容としては、「送り出し機関Aは管理費も何も支払わなくてもいいと言っているけど、オタクはできないの。送り出し機関Aに替えちゃうよ。」という話の仕方をします。
悪質な受け入れ企業とは、契約書不履行、賃金/残業代の未払い、セクハラ、パワハラ、暴力などです。11月1日前後の新制度移行期に多数の問題が新聞、テレビ、雑誌などに載ったので、ご覧になった方も少なくないかと思います。
問題ばかり、書き連ねていますが、私は、外国人人材の受け入れについては、賛成です。日本の人手不足の現状を考えれば、外国人に頼る以外の道がありません。新制度移行に伴い、日本側での法律違反に対する罰則も厳しくなり、監査もこれまでに比べれば、厳しくなるでしょう。ただ、技能実習生制度が抱える全ての問題は、日越双方の原因が複雑に絡み合っており、どちらか一方だけが改善すれば、良くなるというものでもないのです。制度も変わり、介護技能実習生が始まるこのタイミングで、日越双方のこの制度に関わる全ての人間が、法を理解し、制度を理解し、Win-Winになることを願ってやみません。