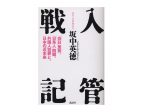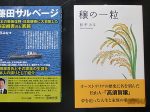日振協が日本語学校研究大会を開催 実践研究の意義を多文化共生・ナラティブ・コミュニティの視点から探る

日振協が日本語学校研究大会を開催 実践研究の意義を多文化共生・ナラティブ・コミュニティの視点から探る
日本語教育振興協会(日振協)主催の令和7年度日本語学校研究大会が、8月7日・8日の両日、東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターで開かれた。テーマは「今こそみんなで教育実践を共有しよう」。武蔵野美術大学グローバルセンター長・三代純平氏が「日本語教育における実践研究の意義と方法―多文化共生・ナラティブ・コミュニティの視点から」と題し基調講演を行った。
日振協の理事長は、創設以来トップに座にいた佐藤次郎氏に代わり、インターカルト日本語学校校長の加藤早苗氏が新たな理事長に主任。加藤新理事長にとって初の日本語学校研究大会となった。
大会初日は、文部科学省の降籏友宏日本語教育課と出入国在留管理庁政策課の山形正洋調整官がそれぞれ日本語教育施策、育成就労などについて講演した。基調講演では三代氏が、日本語教育における実践研究を「現場の課題や実践を省察し、改善を繰り返す営み」と定義。単なる効率化や理論追求にとどまらず、社会的合理性や公正性の向上を目指す点に意義があると述べた。アクションリサーチの枠組みを活用し、参加者が自己省察的に実践を改善すること、そして「実践=研究」として現場の知や経験を次の実践の資源とする姿勢の重要性を強調した。
また、ナラティブ(物語)を重視した研究手法についても解説。複数の立場や声が響き合い、新たな意味を生むことを肯定し、外国人と日本人を支援する/される関係ではなく「共に生きる仲間」として関わる多文化共生の実践例を紹介した。さらに、企業・地域・他分野との協働、教師同士・学校同士による知の共有、日常の小さな気づきや変化を研究の出発点とする姿勢の重要性を説いた。
最後に三代氏は、理念と現場のマニュアル化とのギャップや実践の難しさにも触れ、「楽しい経験を経験のまま終わらせず、なぜ楽しかったかを省察し、次の実践につなげることが大切」と締めくくった。参加者は、日々の教育活動を振り返り、他者と共有しながら質の高い日本語教育を目指す決意を新たにしていた。
これに関連して「日本語・スペイン語・ドイツ語教育実践者が語る工夫と実践」と題したパネルディスカッションが行われた。それぞれの言語教育における実践例などがしょうかいされた。
2日目は分科会と個別のテーマで自由研究の発表があり、多くの参加者が日本語教育の研鑽を積んだ。