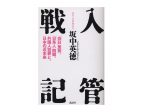- Home
- 2019年度 大養協 秋季大会シンポジウム 新時代における外国の子どもの教育人材に求められる資質・能力を考える
2019年度 大養協 秋季大会シンポジウム 新時代における外国の子どもの教育人材に求められる資質・能力を考える
- 2019/10/2
- 1,303 comments
日本、〒141-0022 東京都品川区東五反田3丁目16−21
外国の子どもの教育支援に関わる人材に求められる資質・能力について,ゲストスピーカーの話と報告書を手がかりに,今後の養成,育成はどうあるべきかを考えていきます。
開催日 2019年11月9日(土) 13:00-16:10
会 場 清泉女子大学1号館140教室,143教室
参加費 会員1,000円,非会員1,500円
参加申し込み こくちーずプロ
https://www.kokuchpro.com/event/daiyokyo19_autumn/
プログラム
13:00-13:10 代表挨拶:山本 忠行(大養協代表理事・創価大学)
13:10-13:20 趣旨説明:中川 祐治(大養協理事・福島大学)
13:20-14:40 ゲストスピーカーによる話題提供
・浜田 麻里氏(京都教育大学)
・田中 宝紀氏(NPO法人青少年自立援助センター )
・今澤 悌氏(甲府市立大国小学校)
・浮島 とも子氏(文部科学副大臣)
*浮島氏については,公務の都合上,予定が変更となる可能性があります。予めご了承ください。
14:50-15:40 グループワーク
15:40-16:10 報告・共有
開催趣旨
グローバル化,世界的な人の移動が進む今日にあって,従来の教育では対応しきれない新しい時代の到来に私たちは直面しています。このような時代の要請を受け,ほぼ同時期(2018,2019年)に,文化審議会国語分科会からは『日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)』が,日本語教育学会からは文部科学省の委託を受けた『外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業―報告書―』が出されました。そこではいずれも当該教育に関わる人材の資質・能力について言及されており,今後の教員養成を行う上でも,当該教育人材に求められる資質・能力とは何か,それをどのように育成すればよいかというのは非常に重要な課題となると考えられます。今回のシンポジウムでは,外国の子どもの教育支援に関わる人材にスポットを当て,当該教育人材に求められる資質・能力とは何かについて,ゲストスピーカーの話と両報告書を手がかりに議論し,理解を深めるとともに,そこでの議論をふまえて,今後の人材の養成,育成はどうあるべきかをグループディスカッションを通して主体的に考えていきます。
お問い合わせ先
大養協事務局: daiyojimu@gmail.com
大養協HP: https://daiyokyo.com