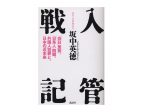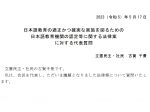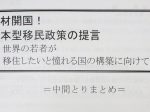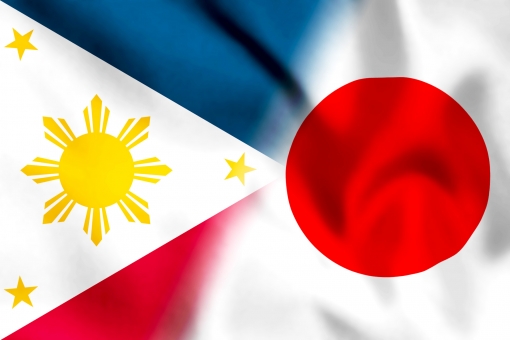
人生の夢の扉
戎 香里菜
学ぶことは生きること。学びは人間らしく生きるために不可欠です。
私が夜間中学校で学んだのは、ただの数字や文字の読み書きだけではありません。空っぽだった心の中の何かが満たされてゆくように、私は成長しました。言葉でうまく表現できないのですが、夜間中学に通えたおかげで、私の中の孤立していた島が、だんだんと向こう側とつながってきていることに気づきました。
私が生まれた家庭は、教育とは無縁の世界でした。フィリピン社会にあるのに、社会とはまったく隔絶した家。ただ、今日どう食べるかしか、考えない両親。私は自分の給料から、服も学費も払っていましたが、だんだんできなくなって、学校には行けなくなりました。両親の離婚後は、親戚をたらい回しにされ、他人の間も転々としました。私も、私の心を空っぽにするしかありませんでした。犯罪組織に監禁されていた私を、国家警察が救い出した時、身元引受人になってくれる親戚は、誰もいませんでした。
一人ぼっちで、希望のない、生き地獄のような人生。
こんな境遇になったのはなぜか?両親に、親戚に、教育がなかったからです。この負の連鎖を私で断ち切りたい。だから25年間「私は、学校へいきたい!学びたい」と涙を流しながら、ずっと心の奥で叫んでいました。
年を重ねても必ず学校へ通い、卒業すること。しかし、私の母国では、年を取った人が学びなおすことは経済的にも、周囲からの眼からも困難です。
ところが日本には、学びなおすチャンスをくれ、むしろ応援してくれるところがあったのです。夜間中学校です。
私の人生の夢の扉を開いてくれたのは、丸山中学校西野分校でした。
もっと早く知っていたらと思いますが、知っていても、淡路島から通うのは無理だったでしょう。市外からは入学さえ許可されません。
当時、息子が通っていた小学校の大下校長先生が、私を兵庫県の多文化共生サポーターとして推薦して下さいました。家の事情で、淡路島から神戸市に引っ越し、尼崎市の琴城分校にタガログ語サポーターとして派遣されて、生まれて初めて夜間中学校というものに出会いました。
熱心に学ぶ様々な年齢、国籍の人。ありのままで受け入れられる学校。
「やっぱり、私も学校へ行きたい。」
懇願すると、居住地にある西野分校を紹介してくれました。通うことになったときの嬉しさは、ことばで表現できないぐらいでした。
今私は、定時制高校3年生です。今の夢は、大学で学び、国連で働いて私と同じような境遇の人たちの力になることです。
学校を必要としている人が、たくさんいます。社会人となって、「今さら、」とか「学校へ行っていなかったことがばれるのがいや」という人も、心の奥で「学校で学びなおしたい」と思っているでしょう。
実は、日本人の私の夫も、時間の余裕があったら、「必ず学校で、学びなおす」と 意志を持つようになりました。そのときに、彼を応援したいと思います。
淡路島にも夜間中学校があれば、学びなおしたいという人がいます。私を見て、学校へ行きたいと言っています。
また、日本人の知人にも、名前と住所しか書けず、区役所からの大事な手紙が読めない人がいます。
バブル期、日本に働きに来た多くのフィリピン人の中に、中学校を卒業出来なかった人がたくさんいます。今も日本で暮らし、きっと、学校へ行きたいと思っているでしょう。
夜間中学と出会えた私たちが、見本となって勇気づけたいと思います。
私たちも、知らなかったことを、知りたい。皆が学んだことを学びたい。
どうか、学び直したい人を、学校にいかせてあげてください。学校で学べない人を、この日本国から なくしてください。
一人でも多くの人に学校の扉を開いてください。
人生の夢の扉を。