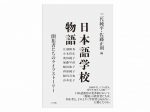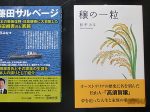- Home
- 増やせ「日本語人口」
- 中小企業127万社が後継者不足で廃業の危機 「日本語人口」増やし優秀な外国人材を後継ぎに
中小企業127万社が後継者不足で廃業の危機 「日本語人口」増やし優秀な外国人材を後継ぎに
- 2018/5/5
- 増やせ「日本語人口」
- VCIアカデミー, 後継者, 日本語人口, 阿部正行, 高度人材
- 1,896 comments

中小企業127万社が後継者不足で廃業の危機 「日本語人口」増やし優秀な外国人材を後継ぎに

中小企業の後継者不足が深刻化している。高齢で引退した社長の後継ぎがいないため廃業に追い込まれる例が少なくない。2025年には127万社が後継者不足で存続の危機に直面するという。雇用の7割を抱え、日本経済の土台を支える中小企業。その危機を救う手立てはないのか。外国人の労働力といえば、技能実習制度などで低スキルの人材を受け入れるケースが大半だが、中小企業を救済する高度人材はいないのか。
「廃業 or 承継 大量引退時代の最終決断」――経済誌「週刊ダイヤモンド」1月27日号でこんな特集を組んでいる。その記事では「中小企業庁が衝撃的なシナリオを提示した。日本の企業の3社に1社が2025年に廃業の危機を迎えるというものだ。6割以上の経営者が70歳を超え、半数の企業で後継者が不在――。大廃業時代が足音をたてて迫っている」と警鐘を鳴らす。
特集によれば、後継者が足りないため、127万社が廃業の危機に陥り、650万人の雇用を失う。その結果、22兆円分ものGDPが喪失する恐れがある、という。まさに「恐怖のシナリオ」だ。しかも、東京商工リサーチによれば、廃業する企業の約半数が経営黒字なのだ。「優良企業が大量に退出していく姿は異様にも映る」と嘆く。確かにショッキングな話だ。
特集では、その対策として「後継者不足や経営難の中小企業を第三者へ売却(M&A)」や「事業承継支援の担い手として期待がかかる全国の地方銀行」を取り上げるが、中小企業が自力での事業を承継できる道筋までは示していない。もとより現状では、中小企業は自らお後継者不足に対しては、思考停止の状態にあるようだ。
そもそも、中小企業の経営者は販売、営業などを一手に仕切るワンマン社長が少なくない。そうした数十万人の「団塊の世代」の社長が2020年ごろに引退時期を迎えるが、少子化や身内に家業意識が薄れていることもあり、後継ぎを育成するより「廃業」を選択する社長が多いが現状だという。

だったら、外国人の高度人材を中小企業の後継者にできないのか。外国人労働者127万8000人(2027年10月末)のうち専門的・技術的分野の在留資格を持つ「高度人材」は23万8000人いる。政府は高度人材の彼らに起業を促し、起業に関わる規制を緩和する方針だという。彼らへの期待はあるのだ。ただし、前提となるのはレベルの高い日本語能力とビジネスセンスだ。専門知識やそれなりの事業資金や意欲も不可欠だ。
中小企業の後継者となるには、さらにいくつかのハードルを越える必要がある。何より経営者の信頼を得なければならない。人並み以上のリーダーシップ、経営者としての資質も欠かせない。関係会社など得意先との付き合い、日本的のビジネスの流儀も求められる。そんな外国人材をどう探すのか。
一方、中小企業の側も、発想の転換が迫られる。優秀な人材は、国籍や民族を問わず優秀である。むしろグルーバル化が進み、外国人材が持つ多様な発想を事業に生かそうという積極さが重要になる。「外国人なんて…」などと考えていては、前に進めない。数ある原石の中から宝石を探し出し、磨き上げるような人材育成への努力がなければ、外国人材を後継者にすることはできない。実際、東大阪市のある中小企業では、経営者が雇用した中国人留学生の高い能力に目をつけ、将来、自分の後継者にしたいと経営のノウハウを学ばせているという。
ハノイのVCIアカデミーは、ベトナム人のトップクラスの大学を卒業した若者に日本語と日本社会の基礎知識やビジネスマインドを教え、日本の中小企業に正社員として就職させる人材会社だ。設立から11年でハノイ工科大やハノイ貿易大など出身の約300人が日本の中小企業で働いている。管理職に昇進し、役員にまでなった人材もいる。
代表の阿部正行氏は「VCIアカデミーはまだ歴史が10年余り。就職先の中小企業では中堅幹部も少しずつ増えてきたが、社長になったケースはまだない。しかし、VCIから複数のベトナム人を採用していただいている東北地方のある農業関係の会社では、社長がベトナム人社員を将来、分社化した会社の責任者にしたいと話していた。ベトナム人を後継者にする企業が現れる可能性はあるだろう」と話す。
阿部氏はハノイ在住26年。人材育成の経験から「日本に行ってサムライになろう」というベトナム語の著書を出版し、発行部数は1万部を超えた。ベトナムではベストセラーだ。日本で働くにあたっての心構えを説く本だが、ベトナムで「日本語人口」が増え、日本語を理解する多くの優秀な人材の中から「サムライ=社長」を夢見る若者が育つかもしれない。