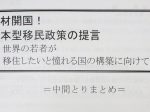改正入管法成立 政府は「共生」にどう向き合うのか
- 2018/12/8
- 多文化共生, 時代のことば
- 194 comments

改正入管法成立 政府は「共生」にどう向き合うのか
外国人労働者の受け入れを拡大する入管法改正案などが12月8日未明に参院本会議で可決、成立した。来年4月に「特定技能1」「特定技能2」の新たな在留資格が創設される。一方、政府は年内に「外国人材受け入れ・共生のための総合的対応策」をまとめるという。外国人受け入れの枠組みづくりに加え、政府は共生のためのどのような「対応策」を打ち出すのか。受け入れ後の仕組みづくりにこそ、私たちは注目すべきだ。
政府は「移民政策をとらない」と強調しているが、一般に移民政策とは出入国管理政策と社会統合(多文化共生)政策を合せたものだと言われている。今回の改正入管法によって政府は外国人動労者受け入れの新たな「入り口」を拡大した。今後、明らかにされる「総合的対応策」は社会統合政策にあたるものだと思われる。対応策は法律ではなく、省令によって定められるので国会の議決は必要ないが、その重要度から見て、よりレベルの高い政治的な議論が求められそうだ。
今回の入管法改正論議では、野党側も人手不足を解消するための外国人受け入れそのものに反対したわけではない。だが、「特定技能」がとかく批判の多い技能実習制度の“延長線上”にあり、そもそも人権侵害など問題が多々ある技能実習制度に関する野党側追及に政府が十分な答弁ができなかったことで議論が紛糾した。
しかし、外国人の受け入れ問題をめぐって与野党が国会で激しい論戦を展開したのは初めてのこと。その議論の高まりを受けてマスコミ報道が過熱した。かつてないほど国民の関心も高まった。自民党内の一部からは反対論も出たが、保守を支持基盤にしている安倍首相が決断した方針だけに、反対の声も終息。野党の国会での反対は、「数の論理」でねじ伏せた。
ただし、本当に重要なのはこれから出てくる「総合的対応策」だ。どこまで政府が踏み込んだ「共生策」をとれるのか。ひと言で「共生」と言っても、その幅は広い。受け入れた外国人の生活全般に関わる事案があるからだ。雇用、福祉、医療、教育など数え上げたらきりがないが、その基盤を成すのか日本語教育だ。日本人と外国人のコミュニケーションが取れなければ共生社会どころではない。
野党は国会で技能実習制度の「ゆがみ」を追及の材料にした。確かに問題点は少なくない。だったら2016年に「技能実習制度適正化法」が国会に提案された際、もっと厳しく追及しなかったのか。
こうした政府の動きとは別に、超党派の日本語教育推進議員連盟(河村建夫会長)がこのほど日本語教育教推進法案をまとめた。日本語議連はグローバル化が進む中で日本語教育に関する法整備が必要だとの問題意識から2016年11月に発足し、議論を重ねてきた。日本語教育関係の有識者から意見を聴くとともに、省庁担当者とも協議しながら法案を作成した。日本語教育推進法案は年明けの通常国会に提出されるとみられるが、日本語教育関係の省庁担当者は政府の総合的対応策に作成も関わっているはずで、日本語教育に関しては現実的かつ効果的な事業展開が期待される。
今回の改正入管法問題に関して、海外のマスコミはほとんど関心を寄せなかったようだ。すでに移民問題が重要な政治課題となっている国にとって、日本は周回遅れの対応のように見えるかもしれない。とはいえ国内的には「日本の国の形を変えるもの」との声が出るなど関心が高い。
参院法務委員会の参考人質疑で、高谷幸大阪大大学院准教授は「外国人が人間として暮らせるための権利と尊厳を保障しなくてはならず、外国人住民基本法、差別禁止法など、多文化社会のインフラが必要だ」と述べた。
これから出てくる政府の総合的対応策の中身の吟味、日本語教育推進法案の成立に向けた動きなど、取り組むべき課題はなお山積している。年明けの通常国会でより中身の濃い議論は求められる。政治の責任は重い。
にほんごぷらっと編集部