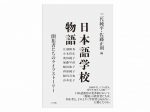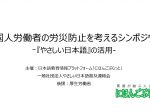◎労働力不足はまずは農業分野で「特区」と「特定活動」で外国人労働者受け入れに対応。
自民党の特命委員長の木村議員が講演で「コペルニクス的転回」と強調
自民党政務調査会の労働力確保に関する特命委員会の木村義雄委員長(参院議員)が18日、都内で開いた多文化社会研究会主催の多文化フォーラム(講演とパネルディスカッション)で、農業分野の外国人受け入れについて、零細中小農家が実施している技能実習制度を維持するとしながらも、農業特区を活用し新たな受け入れ策として特定活動の中に農業を加える考えを示した。特定活動は法務大臣の判断で職種を増やすことが可能で、木村氏は介護などにも広げる考えにも言及した。政府は今後の労働力確保の在り方について、国際的に「人身売買だ」などと批判を浴びている技能実習制度から、特定活動に大きく舵を切る可能性が出てきた。
同特命委は昨年5月に「『共生の時代』に向けた外国人労働者受け入れの基本的考え方」という文書を作成した。この基本的な考え方に沿った形で特命委は法務省、厚生労働省、農林水産省などと協議し、政府・与党は今国会で国家戦略特区に限って外国人の農業分野への就労を認める特区法を改正する方針だ。
基本的な考え方は、「移民」という言葉について、「入国の時点でいわゆる永住権を有する者で、在留資格による受け入れは移民に当たらない」と新たな定義を提唱した。その定義に従えば、「移民」は日系3世までのブラジル人など限られる。それ以外は移民に当たらないという解釈だ。移民受け入れに慎重な安倍内閣の方針にぎりぎり配慮した判断と言える。
また、政府が雇用対策基本計画の中で外国人の入国を規制する方策として用いられてきた「いわゆる単純労働者」については、「明確な定義がない」として政府が使う用語としては不適切だとした。そもそも在留資格を「単純労働者」と「高度人材」という概念で区分してきたことが問題だ。農業など一次産業は「単純労働」に区分されるわけで、職業に貴賤はないといいながら、政府、労働組合、マスメディア、さらには研究者も含め、50年間もこのような無神経な言葉遣いを容認してきたわけだ。
木村氏は内部の議論の過程で政府側が「単純労働」の具体的な事例について「包装」「運搬」「清掃」を挙げたエピソードを紹介。役人がイメージのみで三つの職種を軽視したことを厳しく批判した。この用語の使用を不適切だと断じたことを含め、政治主導で作成した特命委の「基本的考え方」について、木村氏は「(外国人が)堂々と表から入っていただける提言」「コペルニクス的転回の中身となっている文書」と自賛した。
また、木村氏は海外の大手マスメディから自身に取材が相次いでいることを明らかにし、日本政府が過去に例のないような急テンポで進む人口減少に対し、どのように対応しようとしているか、国際的に大きな関心を集めていると述べた。外国人労働者を適正に受け入れなければ日本の経済は落ち込む一方で、その政策いかんによって日本が「売りか買いか」の判断材料になる、というわけだ。国際投資家が日本を「売り」と判断した場合は、株価が大きく下落し、経済は低迷し、日本はそれこそ「落日の国」になってしまうということだ。
講演のあとは、会場からの質疑と、多文化研理事長の川村千鶴子大東文化大名誉教授をコーディネーターに、木村氏に加えて佐藤由利子東工大名誉教授、明石純一筑波大准教授によるパネルディスカッションが行われた。
この中で佐藤准教授は106万人を数える外国人労働者の内訳などを説明したあと、①外国人と日本人のコミュケーションのとり方②トラブルが起きた場合の相談窓口の開設③地方自治体の負担とその支援策――について質問。また、明石准教授は「もったいない」をキーワードに技能実習制度に関わる申請時の莫大なコスト負担のほか、3年しか働けずに帰国せざるを得ない現行の制度では、韓国や台湾に人材獲得競争に勝てないと主張。また、将来の永住や就職などのインセンティブを与えていないことで働き手としてのスキルの向上や意欲がそがれていると指摘した。
これに対し木村氏は、基本的な考え方をベースに農業分野における技能実習制度の在り方について説明し、①特定活動による労働者の受け入れは大手の人材会社に仲介させることで様々な問題解決はその会社に責任を持たせる②技能実習制度で来日し、3年間勤めた後、優秀なスキルを持った外国人が希望すれば特定活動のビザで引き続き働くことができるようにする③農業特区では季節によって労働需要が変わるので仕事を移動できる季節労働を想定している――などと述べた。
また、木村議員は技能実習制度に関して監視機構を発足させることに関連して、「外国人雇用庁に向かっていくような一歩として作らせた」と語り、将来の外国人労働者の受け入れの窓口一元化をにらんだ組織再編であるとの考えを明らかにした。(了)
【解説】鎖国の扉を開けた木村ペーパー
木村義雄氏は、自身がリーダーシップをとって作成した「基本的考え方」を「コペルニクス的転回」と称した。木村ペーパーともいえるこの文書が明らかになった時、マスコミがこぞって大きく報じたという記憶はない。しかし、木村氏の講演での自画自賛はあながち過度な自己PRではない。一つは全くの官僚主導の外国人受け入れの政策を政治主導に導いたこと。もう一つは政府の「鎖国政策」の扉をこじ開けたことだ。
政府は「外国から高度人材は積極的に受け入れるが、いわゆる単純労働者の受け入れは慎重であるべきだ」との方針を半世紀も堅持してきた。しかも法律で決めたわけでない。厚生労働省の方針である「雇用対策基本計画」を閣議決定することで「しばり」をかけてきたのだ。その方針は、高度人材を受け入れるというより、単純労働者は受け入れないことに大きなウエートが置かれていた。基本的には「いわゆる鎖国政策」をとってきたのだ。だからこそ、木村氏が言うように外国メディアはそこに注目している。
しかし、政府と同じ目線でしか取材をしない日本のメディアには何のことがわからないのだ。政府が「移民」という言葉を使わないから大手メディアも移民というと腰が引けてしまう。その意味では九州のブロック紙である西日本新聞社が昨年12月から「新 移民時代」と題した長期連載を掲載していることは注目に値する。正面から「移民」というワーディングをタイトルに据えたのは英断だ。地方都市では、人口減少による経済の疲弊は想像以上に深刻なのだ。
木村ペーパーが作成されたように、政治の世界で人口減少に危機意識が深まっているのは事実だ。自民党政務調査会の特命委員会で方針を打ち出したことは、政府に対して大きな影響力を発揮できる。自民党1億総活躍推進本部の誰もが活躍する社会をつくるプロジェクトチームが留学生受け入れ等の管理や規制緩和などの提言をまとめている。さらには、超党派の日本語教育推進議員連盟が昨年11月に発足した意味も極めて大きい。外国人に対する日本語教育はグローバル時代にあって、最重要のインフラ整備だ。こちらの動きにも期待したい。
木村氏は講演で農業分野に外国人受け入れに関して「農林の方から(日本語能力試験の)N4でどうかと。おまえら馬鹿じゃないか。牛や豚が日本語をしゃべるか」と冗談めかした「秘話」を披露したが、一方で「最低限の日本語ができるようにする」とも明言した。
日本語教育は、留学生が大学や専門学校に進学するための教育メソッドが主流だったが、「やさしい日本語を」含め多種多様な日本語教育が求められている。「人口減との戦い」の波紋が広がっている。