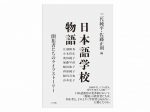即戦力の労働者求め外国人受け入れ枠を大幅拡大 政府は骨太の方針に
- 2018/6/6
- ぷらっとニュース
- 単純労働, 経済財政諮問会議, 骨太の方針
- 202 comments

即戦力の労働者求め外国人受け入れ枠を大幅拡大 政府は骨太の方針に

政府の経済財政諮問会議が5日開かれ、出席した安倍晋三首相は「地方の中小、小規模事業者の人手不足は深刻化している」と強調し、「一定の専門性・技能を持つ即戦力の外国人材を幅広く受け入れる仕組みを早急に構築する」と述べた。6日の日本経済新聞が詳しく伝えている。
日経新聞によると、建設や農業、介護など5つの分野を対象に2019年4月に新たな在留資格を設ける。原則認めていなかった単純労働に門戸を開き、2025年までに50万人超の就業を目指すという。政府はこうした方向を今月中旬に閣議決定する経済財政の基本方針(骨太の方針)に明記。秋の臨時国会には入管法の改正案を提案する。
さらに、新たな在留資格については2つの方法を提示する。1つは最長5年の技能実習制度を延長し、実習を修了した後も日本で仕事ができるようにする。2つ目は建設や農業分野では日本語能力が「N4」を原則にしながら、そこに達しないケースも認める。
記事では「日本政府がまず取り組むべきなのは日本語教育だ。行政と企業が連携し、学習機会を提供しなければならない」と主張。そのこと自体は、日本語教育推進議員連盟が作成した日本語養育推進基本法(仮称)の原案に沿ったものだ。
このほか、記事の中で「外国人労働者から『選ばれる国』になるために受け入れ態勢の整備が必要だ」と指摘する。ここは重要なポイントだ。国は責任をもって日本語教育も方策の1つだが、「選ばれる国」になるには、その他の施策も整備しなければならない。すでに日本はアジアでも「給料が高い国」とは言えなくなってきた。安倍首相は「移民政策とは異なる」と述べたそうだ。「移民政策」をどう定義については様々な議論があるだろうが、要は「外国人が住んでみたくなるような魅力を持った国」ということになるだろう。受け入れ枠の拡大の「次の施策」が問われている。
【解説】日系人受け入れ枠拡大の「反省」を忘れるな
日本政府が外国人受け入れに大きく舵を切ったのは、1989年の入管法改正だ。ブラジル、ペールなどの日系人の3世までを対象に「定住」の在留資格を設けたことで、南米からの日系人が急増した。その法改正に携わった学者の「反省の弁」をあるシンポジウムで聞いたことがある。「彼らはデカセギだからお金を稼いだら母国に帰ると思っていた」。ところが家族を呼びせよたり、日本で結婚するなどして定住化が一気に進んだ。その数は一時30万人を超えた。
多くは日本語がしゃべれなかった。近所の日本人との軋轢が生れ、子供は日本の学校に入学しても、授業についていけなかった。非行に走る少年も多く、社会問題としてとらえる見方が広まった。総務省は「多文化共生プラン」という指針を作成した。そここと自体は大きな前進だったが、現実には地方自治体に対応が任された。
2008年のリーマンショックを受け、自動車産業など産業界は一挙に日系人労働者を切り捨てた。まさに外国人労働者は景気の「調整弁」、都合のいい使い捨て労働者だった。政府は帰国支援金として旅費を出したが、体のいい「手切れ金」だった。苦汁をなめた、ある日系ブラジル人は「もう日本にはいかない」と吐き捨てた。日本は外国人にとって「魅力のある国」だったのかどうか。
あれから10年。日本の高齢化に伴う労働力不足は深刻化の度合いが一層、深まっている。安倍内閣は1989年の入管法改正以来の外国人受け入れの大拡大策をとろうとしている。経済財政諮問会議はもちろん部外の専門家からの意見も聞いて方針を決定したのだろうが、「経済財政の視点」からだけで生身の人間の扱いを決めていいのかどうか。技能実習の期間を3年から5年に延ばし、さらに延長することが外国人の家庭に配慮した政策なのか。雇用する側の論理だけでものごとを決めていないか。
移民政策かどうかはともかく、外国人の「生活」について配慮が行き届いた政策は不可欠である。日本人と外国人が共生する社会をどう作るか。2050年には日本の人口は1億人を割り込む。政治にはいま、長期的なビジョンが求められている。